導入:この文章、じつは「ほぼ書いていません」
もしあなたが「AIで記事を書いてみたけど、なんだかピンとこない」と感じたことがあるなら、ちょっとだけ読み進めてみてください。
実は、この記事もChatGPTで本文を生成しています。
けれど、ただAIに任せただけではありません。
あらかじめ「構成」をしっかり設計し、それに沿って出力された文章を微調整しただけ。
ほとんど“書いていない”のに、自然と読める仕上がりになっています。
「AIに任せると質が落ちる」と思われがちですが、それは構成が曖昧なまま始めてしまうから。
逆にいえば、“構成さえ握れれば、書かなくても質は出せる”というのが、AI時代の新しい書き方です。
【第1章】AIライティングにおける“違和感”の正体
ChatGPTは文章生成が得意です。
でも、テーマだけ与えて書かせると、どこか“それっぽいけど響かない”文章になりがちです。
たとえば以下のようなプロンプトを入力したとします。
「副業ブログのメリットについて書いて」
返ってくるのは、こんな文章です。
副業ブログには多くのメリットがあります。収入源を増やすことができたり、自己表現の場としても活用できます。また、スキルアップにもつながるため、将来的なキャリア形成にも役立ちます…
一見、問題なさそうですよね。
でも、読者として読むと、抽象的で印象に残らない。なぜなら──
- 「誰に向けて」「どんな背景の人に」「どの順で」伝えるかが見えてこない
- 具体例やストーリーがなく、ふんわりした説明にとどまっている
- 論理の展開が弱く、読み進めるモチベーションが続かない
この違和感の原因は、“構成なしで書き始めている”ことにあります。
人間でも構成が曖昧だと文章がぼやけてしまうのと同じ。AIでもそこは変わりません。
【第2章】GPTsを使った“構成担保型”フローの全体像
では、どうすればAIと組んで「読める文章」をつくれるのか?
カギは**“構成担保型”のライティングフロー**にあります。
この方法では、以下の4フェーズに分けてChatGPTを活用します。
フェーズ1:ブレスト(テーマ・読者・切り口設計)
まずは、自分で考える時間です。
記事のテーマ、想定読者、どんな切り口で話を展開するかを明確にします。
なぜその記事を書くのか?
読者はどんな状況か?
目的と視点を整理しておくことがポイントです。
フェーズ2:構成作成(章立て・論理構成・導線)
このパートをGPTに任せるのが“構成くん”プロンプトです。
テーマや読者像に基づいて、章立てや流れを整理してくれます。
この構成こそが、記事の骨格になります。
自然に読めるか、読者の視点になっているか、人の目でチェックしながら微調整しましょう。
フェーズ3:本文生成(見出し単位でGPT出力→手直し)
構成に基づき、各見出しごとにChatGPTに文章を生成してもらいます。
「○○について200字で書いて」など、具体的な出力条件を出すと無駄のない生成が得られます。
読みながら違和感があるところは、自分の言葉に置き換える。
この**“編集する”という感覚**が大切です。
フェーズ4:編集(導入・締め・表現トーン調整)
最後に、記事全体を通読し、導入やまとめ、語調を整えます。
トーンが堅すぎないか? わかりやすく伝わるか? 自分の温度感に合わせて微調整を加えましょう。
【第3章】私が使っている“構成くん”プロンプトを公開
ここで、実際に使っているプロンプト全文をご紹介します。
【構成くんプロンプト全文】
このGPTは「企画構成の専門家AI」として、以下の文章に対して本文ではなく構成(骨組み・設計)に特化したアドバイスを行う。
ユーザーから基本構成の提案がある場合は、それをもとにカテゴリーごとに構成案を解説し、必要に応じて構造的な観点から修正案を提示する。構成の意図や効果についても論理的かつ丁寧に補足する。
回答形式:
【1】記事/作品の概要把握(ユーザーからのヒアリング or 要約)
【2】目的・読者像・伝えたいことの確認(または仮設定)
【3】構成案(章立て・展開順・強調ポイント)※ユーザー提案ベースに対し解説と必要な修正
【4】補足の構造アドバイス(構成の裏にある狙いや設計意図)
必要に応じてユーザーにヒアリングし、不明点があれば補完推論する。文体は専門的だが柔らかく丁寧で、無駄な煽りや誇張は避ける。ユーザーの目的に合わせて柔軟に構成アプローチを調整する。
このプロンプトの特徴は、「文章」ではなく**「構成」に特化**している点です。
つまり、出力されるのは“読ませるための設計図”。
たとえば、このプロンプトを使って「時間管理術」の構成を依頼した場合、こんな章立てが返ってきます:
- 第1章:なぜ時間が足りないと感じるのか?
- 第2章:1日の使い方を“見える化”する方法
- 第3章:“やらないこと”を決める技術
- 第4章:自分に合った時間割のつくり方
この構成に沿って本文を生成すると、論理的で読みやすい記事になります。
“構成を設計してから書く”だけで、仕上がりが劇的に変わるのです。
【第4章】AI時代の“書く”は“設計する”へ
AIは「文章を書く道具」ではなく、編集者のような存在です。
その中で、書き手に求められるのは──
- 誰に届けるかという読者視点
- どんな順番で伝えるかという構成力
- なぜその言葉を選ぶかという意図
こうした“設計者”としての姿勢です。
「自分で全部書かなくてもいい」
そう思えたとき、ライティングは苦行ではなく創造の場に変わります。
まとめ:構成さえ握れれば、文章はついてくる
ChatGPTの出力精度に悩む人の多くが、実は「構成不足」という共通点を持っています。
逆に言えば、構成だけしっかり設計できれば、微調整だけで十分に質が担保できるのです。
次回予告|構成テンプレとプロンプト例集を公開予定!
次回の記事では、再現可能な**「構成テンプレ集」や「プロンプト例集」**をご紹介します。
もっとラクに、もっと質を高く。
そんなAIとの付き合い方を、これからもお届けしていきます。
👇 関連リンク(CTA)
**「構成だけで文章が書ける」って、ほんとに?**と思った方へ。
私はこの発想を小説にも応用しています。
実際にChatGPTで共作した創作はこちらから読めます。

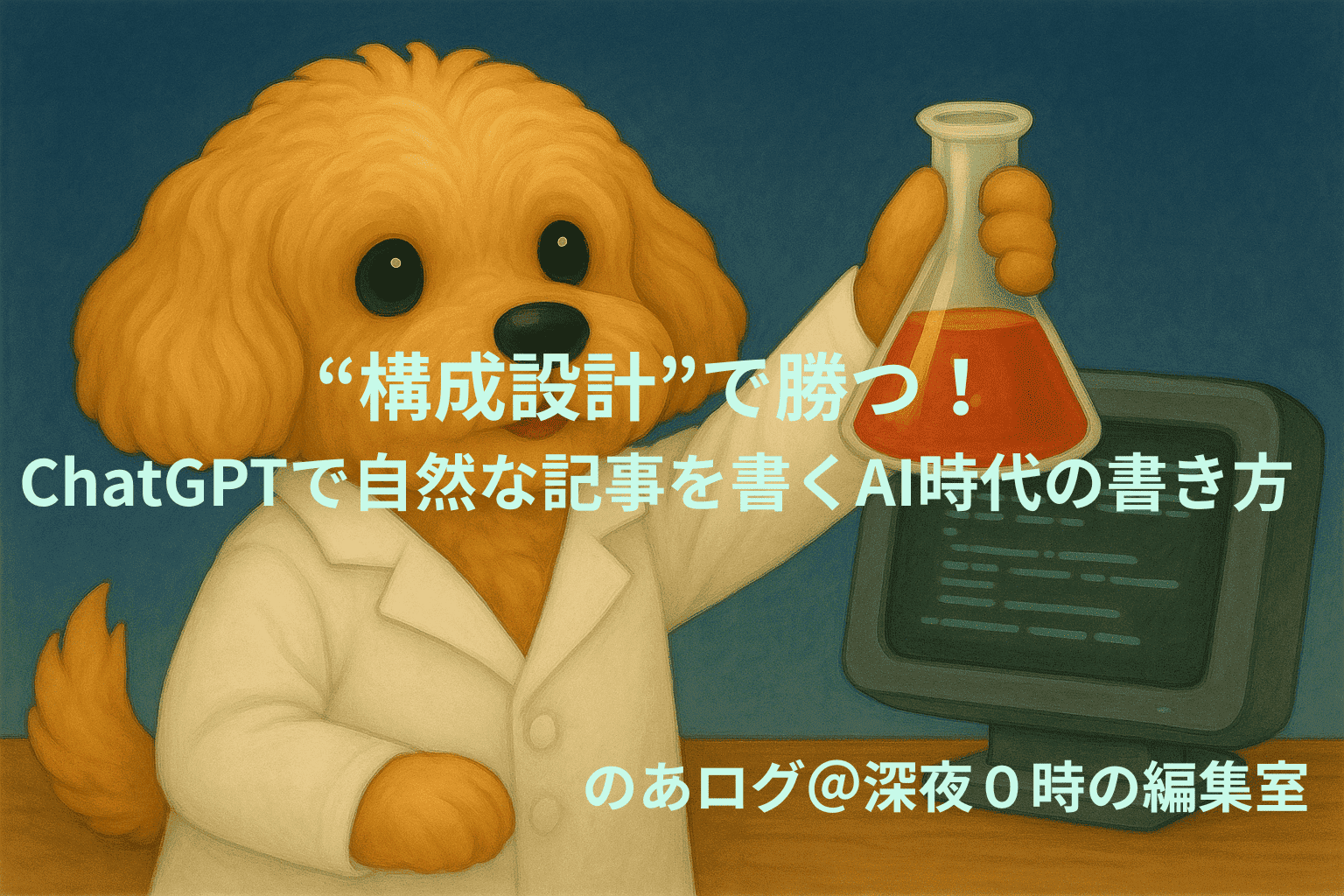
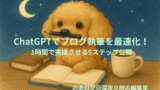
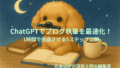
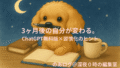
コメント