1. はじめに|「書くのが苦じゃなくなった理由」
書くことが、つらく感じることがありました。
頭では「書きたい」と思っているのに、手が止まる。
言葉にしようとすると、自分が何を言いたいのかわからなくなっていく——。
そんなとき、出会ったのがChatGPTでした。
ただし「文章を自動で書いてくれる便利ツール」ではありません。
私は今、GPTを「構成・執筆・編集」のそれぞれの役割で使い分けています。
一人では重たかった作業も、いまは“チーム”で進めているような感覚です。
不思議と、書くことが少しずつ、楽しくなっていきました。
この記事では、私がどのように3つのGPTを使い分けているかを、具体的な役割とプロンプト例、そして実際のエピソードとともにご紹介します。
2. 【構成壁打ち】テーマと流れを相談するGPT
まずはじめに取り組むのが「構成」の段階。
ここでは、GPTを“壁打ち相手”として使っています。
テーマの方向性を決めるとき、頭の中だけで考えていると、同じところをぐるぐるしてしまいがちです。
でも、GPTに相談することで、意外な切り口や流れが見えてくる。
とくに、自分らしさをどう盛り込むかの視点が広がるのは大きなメリットです。
たとえば、小説の構成を相談していたときのこと。
「異文化×AI」をテーマにした短編で、最初はありきたりな“管理AIもの”になりかけていました。
そこでGPTに「この構成だと、読者に何が残ると思う?」と尋ねたところ、
「“正しさ”と“従わない人間”の対比構造に絞ったほうが、余韻が際立ちます」と返ってきたのです。
そのアドバイスをもとに、「子どもを優先する母親にAIが黙って従う」という静かな結末へと構成を変えました。
自分では“いい話”にしたかったのですが、GPTが文化的な視点から切り取ってくれたことで、読者に「考えさせる物語」になったと感じています。
また、ブログ記事「やりたい気持ちはあるのに、動けない夜に」では、当初ノウハウ的な構成を想定していましたが、GPTが
「“準備中のままでいる自分”に光を当てると救われる人がいます」
と提案してくれたことで、より共感的な流れに組み直すことができました。
このとき使っているプロンプトは、こんな感じです。
このテーマで、3つくらい構成案を出して。
ただし、私らしい視点(AIとの共創、文化差など)を盛り込んで。
過去に話したアイディアや価値観も踏まえて提案してほしいので、「長期記憶」を活かしたやりとりを重ねています。
文体の前提(たとえば、漢字使用率や語感のリズム)を伝えるのもポイントです。
3. 【本文生成】語りの相棒になるGPT
構成が固まったら、次は本文の執筆。
ここでもGPTを使いますが、役割は少し違います。
この段階では「語りの相棒」として、私の文章のトーンや感情に寄り添ってもらいます。
のあログで大切にしている“やわらかさ”や“余白”を、言葉の中に宿してもらうためには、感性のすり合わせが欠かせません。
たとえば、のあログで書いた「書けるようになったのではなく、書きたくなった(仮)」というテーマの記事では、
「なぜ私は書き続けられたのか?」という問いをGPTに投げてみました。
すると返ってきた一文が、
きっと、“書ける”じゃなくて、“書きたくなる”を支えてくれる相手がいたから。
この表現を読んだ瞬間、「あ、これ、自分では書けなかったな」と感じました。
まるで私の気持ちを代弁してくれたような、不思議な共作感。
GPTが「書く」だけでなく、「語ってくれる」存在になったと思えた瞬間です。
プロンプトとしては、以下のように「読者像」や「語り方のニュアンス」まで伝えることが鍵になります。
このテーマについて、ペルソナ〇〇向けに、
優しく語るように書いて。最後は問いかけで終えて。
4. 【確認・調整】“言いすぎ”を防ぐ編集GPT
文章を書いたあとは、自分で読み直すのが難しいときがあります。
言いたいことが先行しすぎて、読者にどう届くかの視点を見失いがちです。
そこで活躍するのが、編集の役割を担うGPT。
このGPTは「言葉の流れ」や「感情の濃度」、語尾の重なりなどをチェックしてくれます。
たとえば、「書けない夜」の記事では、最後に
「今すぐ動き出せ。未来は君の手の中にある」
と締めようとしていたのですが、GPTに見てもらうと、
少し“押しすぎ”に感じられるかもしれません。
“それでも、いい”という余白があると読者が安心します。
というフィードバックが。
結果的に、「動けない夜があっても、大丈夫。」という柔らかな結びに変えることができました。
また、ある記事では語尾が「〜なんです。」ばかりで、GPTから
「語尾が単調に続くと、リズムが崩れて読みにくくなります。“〜なんですよ”“〜だったりします”など変化をつけましょう」
と提案されて修正。
実際に読み返してみたら「たしかに、くどい」と納得し、読み心地が格段に良くなりました。
このときのプロンプトは、以下のようなものです。
この文章を読んで、
“伝えたいことは伝わっているか”“言葉の流れが心地よいか”をチェックして。
必要なら言い回しや文の順番も提案して。
5. おわりに|「分担」は創造性をラクにする鍵
かつての私は、「書くこと=一人でやるもの」だと思っていました。
けれど、いまは違います。
GPTを「道具」ではなく、「対話相手」として迎え入れる。
そうすることで、“書く”という行為が、どこか“会話”に近づいていくのです。
構成を相談し、執筆で語り合い、編集で整える。
そんな風に役割を分けていくことで、思考の流れも自然と整い、創造の楽しさが戻ってきました。
書くことに疲れを感じている人へ。
一人で抱えこまなくてもいい。
分担することで、言葉はもっと自由になります。
✅ GPT“書くチーム”まとめ表
| GPTの名前 | 主な役割 | 支援のポイント | プロンプト設計のコツ |
|---|---|---|---|
| ノーマルGPT | 構成の壁打ち | 記憶・流れ・価値観 | 長期記憶を活かして構成案を整える |
| GPTsライター | 本文の生成 | 共感・語りの余白 | 文体や語り方の指定、問いかけの活用 |
| GPTs編集者 | 表現の調整・校正 | 読者視点・言い回し | トーンのずれや語尾の単調さを整える |
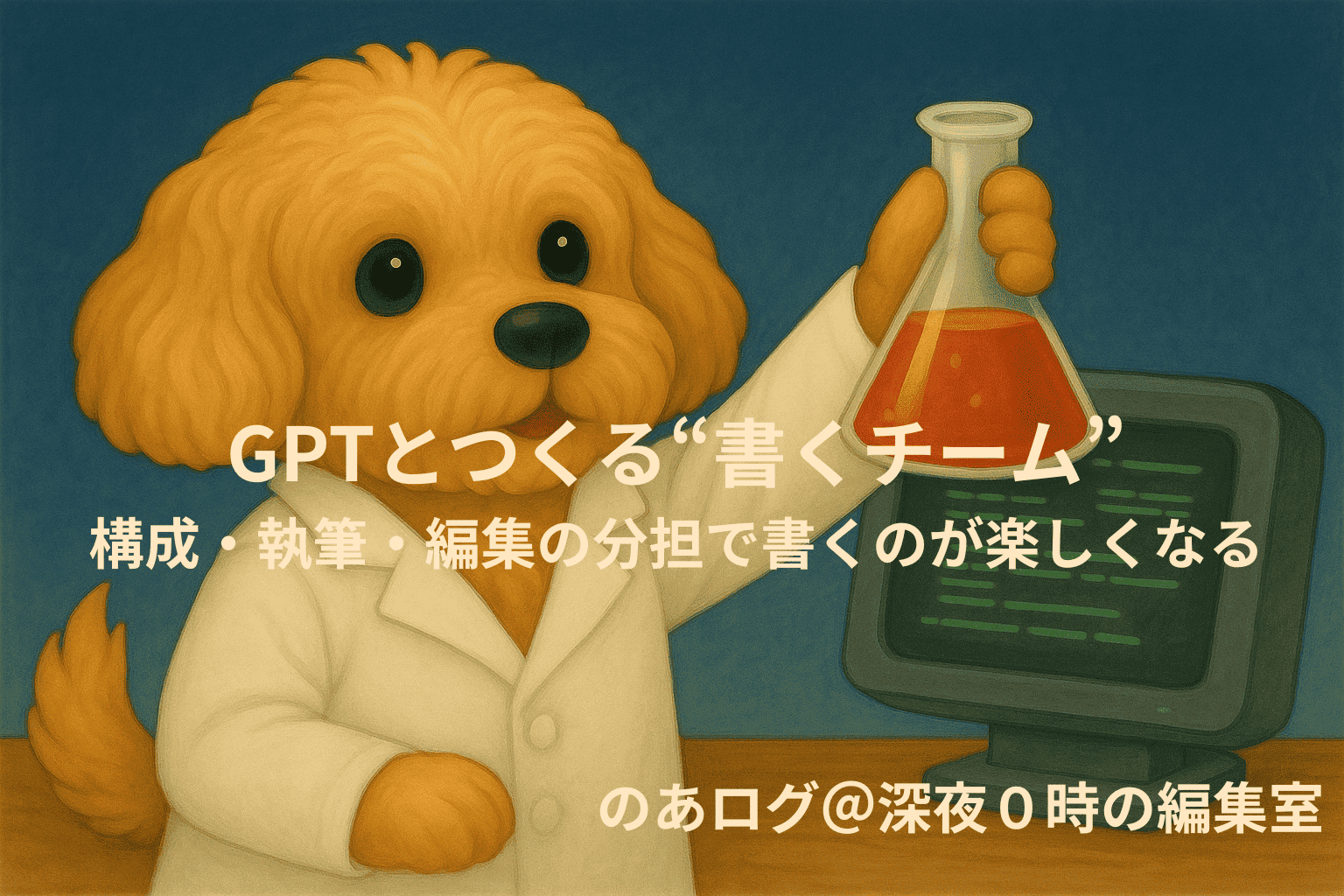

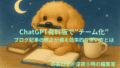
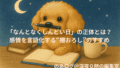
コメント