無料→有料で見えた変化と“修正が減る”工夫
前編では、無料版のChatGPTだけでもブログ記事が書けることをご紹介しました。
慣れれば30分で1記事仕上げることもできるし、AIと一緒に書く楽しさも感じられます。
けれど、使い続けていくうちに、こんな気持ちが芽生えてきました。
「もうちょっと、速く書けたらいいな」
「このあたり、誰かに任せたいかも」
そう思ったときが、次のステップのはじまりでした。
ChatGPT無料版で感じた“限界”と可能性
無料版でも十分に使えます。でも、続けていくといくつかの壁にぶつかります。
たとえば──
- 文体を変えるのが難しい
- 長文の修正が苦手(全体が変わってしまう)
- 構成から校正まで、すべて自分一人で行うワンオペ状態
特に、長文の調整では「全体を整えてください」とお願いすると、思っていたのとまったく違う文章になってしまうことも。
また、「どこまでが自分の言葉で、どこからがAIの文章か」が曖昧になることで、ちょっとした違和感や迷いも生まれます。
それでも、使い方次第でここまでできるのかという“可能性”も確かに見えました。
だからこそ、もっと自分に合った形で「分担」できないかと考えるようになったのです。
ChatGPT有料版で実現した“役割分担”の工夫
そこで、有料版(GPT-4)に切り替えました。
大きな変化のひとつが、「カスタムGPT(GPTs)」を使えるようになったこと。
これは、用途ごとに役割を分けた“AIの分身”を作れる仕組みです。
たとえば、
- 構成を考えるのが得意なGPT
- 語尾や言葉のトーンを整えるGPT
- 読者の視点からツッコミを入れてくれるGPT
というように、それぞれの得意分野を明確にし、目的ごとに相談することで、迷いがぐんと減りました。
「誰に何を聞けばいいか」が明確になるだけで、文章を書くスピードも、クオリティも、自然と上がっていったのです。
修正が減ると、書くのがラクになる
チームGPTを使うようになって感じた一番の変化は、「修正の回数が減ったこと」でした。
以前は、書いたあとで構成を練り直したり、語調を調整したり……と、完成までに何度も手を入れていたのですが、今は最初から“各役割”に分けて相談できるぶん、後から直す手間がぐっと減りました。
結果として、全体の作業時間も自然と短くなり、1記事にかける時間は以前の半分ほどに収まることもあります。
「考える→試す→直す」の流れがスムーズになっただけで、こんなにラクになるんだと実感しています。
ChatGPTが“チーム”に見えてきた瞬間
これまでは「ひとりで書く」「AIに手伝ってもらう」という感覚でした。
でも、カスタムGPTを使い始めてからは、まるで“チームで書いている”ような感覚が生まれました。
ひとつの画面の中に、ちゃんと“チーム”がいた。
自分の思考を分業できるようになったことで、迷わず一歩ずつ進めるようになったのです。
もちろん、最終的に決めるのは自分です。
でも、「一緒に考えてくれる誰か」がそばにいてくれる。
それが、ChatGPTという存在でした。
これは単なるツールではなく、もうひとりの自分。
ときに客観的な視点をくれる編集者であり、ときに励ましてくれる仲間のような存在。
そんなふうに感じられるようになったのです。
私の“チームGPT”紹介
実際に、今私が使っているカスタムGPTたちを紹介します。
● プランナーGPT
思いつきもちゃんと拾ってくれる、やさしい進行役。
構成や見出しを一緒に考えてくれる相棒です。
「このテーマ、どう切り取ろうか?」
「全体の流れが迷子になってないかな?」
という相談にのってくれます。
● コピーライターGPT
ちょっと厳しめだけど、プロっぽい言葉選びをしてくれる存在。
語感や言い回しに敏感な文体調整のプロです。
「この語尾、ちょっと堅いかな?」
「もう少しやわらかい印象にできる?」
といった微調整にぴったり。
● マーケGPT
データでビシッと指摘してくる、頼れる分析屋。
検索ニーズや読者心理に強く、SEOや導線のアドバイスをくれます。
「この記事、検索で読まれる?」
「タイトルにもっと強いワードを入れたい」
といった相談に活躍してくれます。
● 編集長=自分
そして、すべてをまとめて最終判断するのが自分です。
構成・文体・読者目線──それぞれのGPTが出してくれた意見をもとに、どう整えるかは自分次第。
まるで編集会議のように、ChatGPTとやり取りしながら「自分らしい記事」をつくっていく。
それが、今の私の書き方になりました。
実際のやりとりをチラ見せ
チームGPTとのやりとりは、まるで会話のよう。
ちょっとだけ、その様子をご紹介します。
「この語尾ってちょっと堅い?」
→ コピーライターGPT
「たしかに少しフォーマルですね。“〜かもしれませんね”にするとやわらかくなりますよ」
「この構成ちょっと迷子かも」
→ プランナーGPT
「“前提→問題提起→提案”の流れで再構成してみました。見出しはこちらです」
「この内容って検索で読まれる?」
→ マーケGPT
「“◯◯ 初心者”の検索ワードに対して上位表示している記事では、こんな構成が使われています」
AIと話しているというより、“考える仲間とディスカッションしている”ような感覚です。
おわりに|AIと“共創”するというスタイル
AIは、ただのツールではありません。
自分が書くための「余白」や「支え」になってくれる存在です。
使いこなすというより、共に書く。
それが、書くことを続けられる理由になるのだと思います。
無料版でも、十分に書けます。
でも、有料化して「分担できる書き方」に変えたことで、「ひとりで抱えない発信スタイル」が手に入りました。
書くことが孤独じゃなくなる──
それだけで、ブログはもっと楽しく、無理なく続けられるものになるはずです。
あなたの“チームGPT”は、どんなメンバーになりますか?

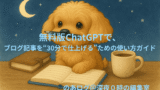
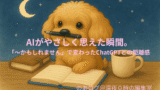
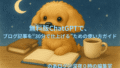
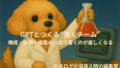
コメント